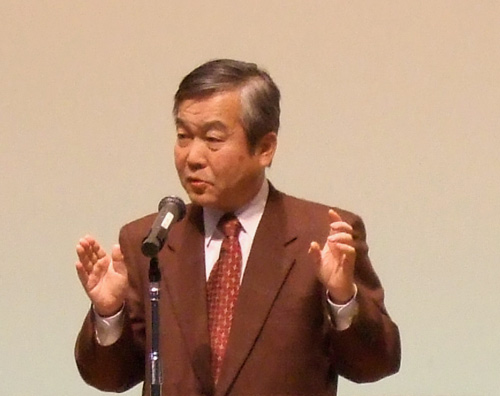「いま、女性が直面する問題に切り込む」
戦前から戦争直後の日本は、産業の中心が農業、商業、家内工業で、女性は労働、家事、育児、介護の‘四重苦’の状況に置かれていました。 やがて高度経済成長期に入ると、家族は夫の収入だけで食べていけるようになります。その結果、多くの女性が「専業主婦」になることが可能となり、 女性の労働参加率は著しく低下します。所得が上がってくると、男女にかかわらず高い教育を受けることが可能となり、女性も学んだことを社会に活 かしたい、働き続けたいという希望を持ち始めます。そこで女性は、①両立して仕事を続ける、②仕事を辞めて専業主婦になる、 ③子育てが終わってから再度働くという3つの中から選択を迫られ、働き続けたい女性にとっては、仕事と子育てなどを如何に両立するかという問題に直面することになるのです。
そして今、1億総中流社会から貧富の格差が広がる社会となってきました。働く女性が増加する中、女性の就業には、学歴の差に加え、男性にはない一般職と総合職の選択が 追加される‘三極化’が起こっているのです。理系に強い女子小中高生も増えている昨今、これからは、女性の‘三極化’や男女の差も大きく変わってくる可能性があります。
このような中で、何をどのようにしていくべきなのか、私は3つの点を主張しています。 まず、1番目は、女性に働き続ける意欲をもって欲しいということです。せっかくの能力と知識を女性も発揮してもらいたい。働き続けていないと離婚した場合に生活に困ることに もなります。また、労働力不足の時代を迎える社会経済情勢から女性が働き続けることが期待されています。 また、男性の働き方の見直しや子育てへの関わり方について子どもの頃からしっかり教育することが重要です。
2番目は積極的な労働政策の実施です。採用や昇進に際する男女の差別を実質的に解消するとともに、 働き続けることを希望する女性が仕事と子育てなどを両立できるための法整備や支援施策を政府と企業が進める必要があります。
最後に、同一労働同一賃金の原則の実現です。男女雇用機会均等法の施行後、男女正規雇用労働者間の賃金格差は縮小してきましたが、 正規雇用労働者とパートタイム労働などの非正規雇用労働者間の賃金格差は拡大しています。女性は男性に比べ非正規雇用労働者が多いことから、 新たな形の男女間での賃金格差が登場しているのです。正規雇用労働を希望する女性がやむなく非正規雇用労働に甘んじるような状況を改善する ことが必要です。欧州諸国では同一労働同一賃金の原則を法律で定める時代になってきました。日本もこの方向に進むべきと期待しています。
大きな変革の時代を迎える今日、女性がどのような生き方をするのかが、重要な視点となります。男女、夫婦が協力して子どもを育てていくような社会になってほしいと思います。